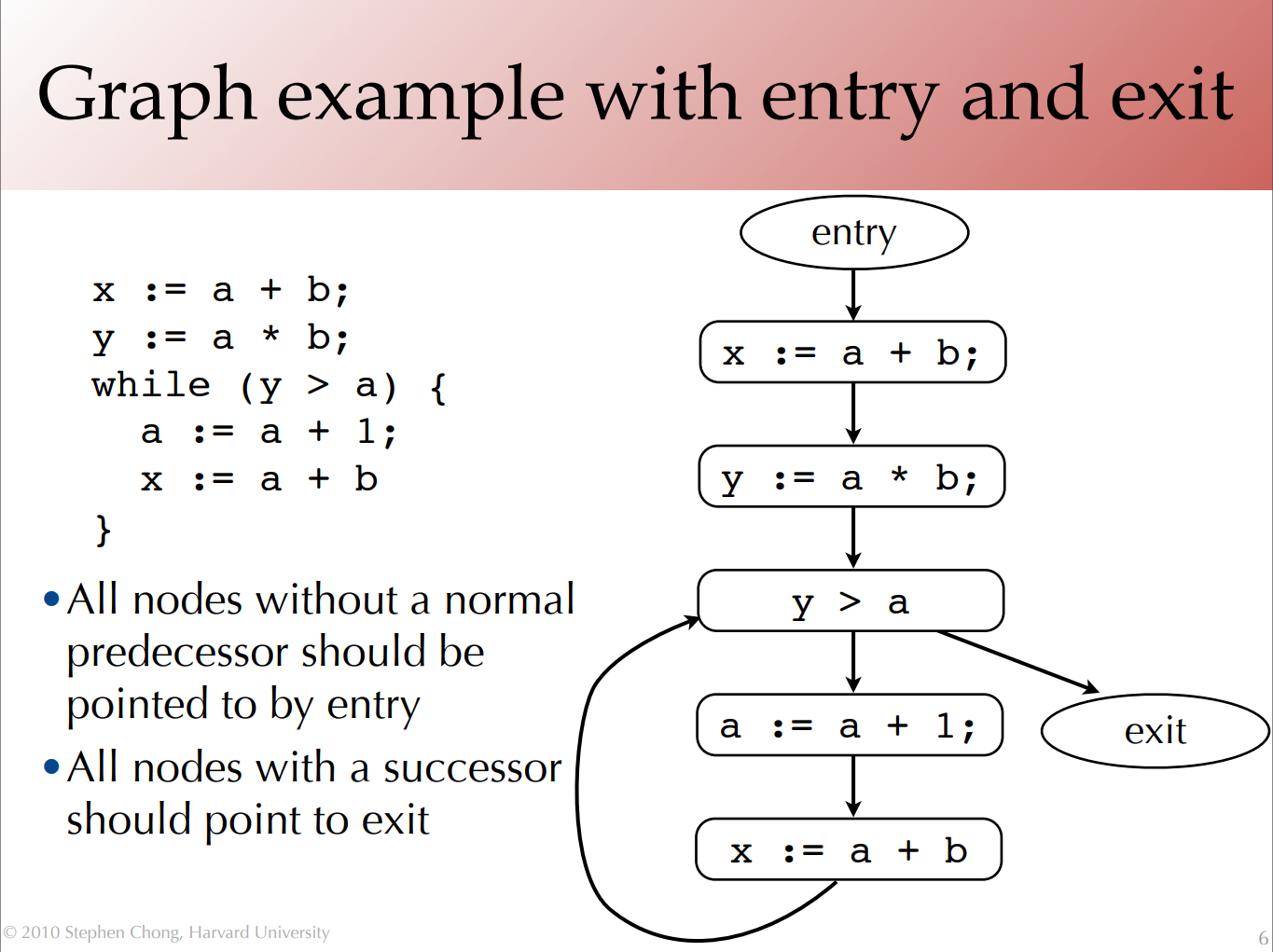危険な脆弱性であっても名前を付けないとなかなか認知してもらえない、といったことがよくあります。「データ検証をしないアプリ仕様」は危険で脆弱な仕様ですが、基本的な対策を実装しない危険性はあまり認知されてないと思います。例えば、とんでもないGDPR制裁金を支払うといったリスクが高くなります。
名前が必要なのかも知れません。
実は新しく考えなくても既にOWASPが名前を付けています。
- Unvalidated Input (未検証入力)
OWASP TOP 10 A1:2004 Unvalidated Inputとして第一番目の脆弱性として挙げています。
2007年版から消えていますが、これはセキュアコーディングとの兼ね合いで省略したのだと思われます。「2007年版から消えているので脆弱性ではなくなったのだ」とする自分勝手な解釈の解説を目にしたことがありますが、その2007年版には「リストから消したが変わらず重要な対策で、本年度版の脆弱性対策の手法としても記載」とする解説が書かれています。
標準的なセキュリティ対策の概念では「入力データ検証は非常に重要な脆弱性対策」です。
(さらに…)